中1で数学につまずく本当の理由
小学校の算数とのギャップが原因
中学に入って最初の数学の壁。それは…
「小学校の算数」と「中学数学」はまったく別の学問
小学校では「計算のやり方」を覚える学習が中心でした。
一方で中学数学では、
- ルールを理解して使いこなす力
- 抽象的に考える力
この2つが求められます。
たとえば、
- 小学校:3 × □ = 12(□に何が入る?)
- 中学校:x + 3 = 12(xとは何か?)
ただこれだけの違いで、混乱する子が急増します。
「正負の数」と「文字式」こそ、最初の関門
中1のつまずきポイントはほぼこの2つ:
- 正負の数(マイナス×マイナス=なぜプラス?)
- 文字式(記号を使って操作する)
これらは「感覚」ではなく「理由の理解」が不可欠。
つまり、説明できるレベルまで理解していないと、すぐに応用問題でつまずきます。
ケアレスミスの正体=理解不足のシグナル
よく「符号ミス」「括弧のミス」と言われますが、実は…
多くが「ルール理解の不十分さ」から来ている
- 符号ミス → 正負のルールが曖昧
- 括弧の展開ミス → 分配法則の本質が不明確
ただの“うっかり”ではなく、理解の見逃しを意味しています。
鷹栖町・旭川の中学生が苦手になる単元TOP3(EIMATHデータ)
第1位:文字式の利用
文章から式を立てるという思考が必要。苦手な生徒の特徴:
- 「xを何にするか」がわからない
- 問題文の読み解きができない
→ 言葉→数式への翻訳力が求められます。
第2位:方程式
「=(イコール)」の意味があいまいなまま進んでいるケースが多発。
- 解き方は覚えているが、理由が説明できない
- 検算をしない/意味がわからない
→ 左右のバランス=同じ状態を保つ感覚の習得がカギです。
第3位:空間図形
立体を頭の中でイメージする「空間認識力」が必要な単元。
- 展開図や切断図を思い浮かべられない
- 公式は覚えていても使いこなせない
→ 図形を“手で動かす”ような思考トレーニングが効果的。
つまずいたときの勉強法|2つの鉄則
① ステップ学習 + 視覚化
ありがちな悪循環:
解く → 間違える → わからなくなる → 嫌になる
これを防ぐには…
- 段階的にレベルアップする設計
- 図・色・チャートで“見える化”
が重要です。
✅ 色分け
✅ 手順のフローチャート
✅ 図を使った理解
こうした手法が「頭の中のモヤモヤ」を解消します。
②「自分の言葉」で説明してみる
理解を深める最短ルートは、
「誰かに説明する」こと
- 親に教える
- 友達に話す
- 塾の先生に口頭で説明する
「言葉にできる=理解できている」の確かな証拠になります。
【自社紹介】EIMATHの「個別解説AI」って何?
EIMATHでは、生徒のつまずきにピンポイントで対応するために、
“単元別の個別解説AI”を提供しています。
📘 特徴:
- 苦手の原因を明確化
- 図解・手順で視覚的に理解促進
- 自分専用AIとして苦手を解決する問題を生成
塾に来れない日でも、このAIさえあればすぐ復習&解決できます。
まとめ|中1数学で「早めの対策」が未来を変える
- 小さなつまずきを見逃さない
- 困ったらすぐに立ち止まる
- 一人で抱え込まない
この3つを意識するだけで、数学への苦手意識は大きく変わります。
「うちの子も当てはまってるかも…?」と感じたら、
まずは気軽に無料体験から始めてみてください!
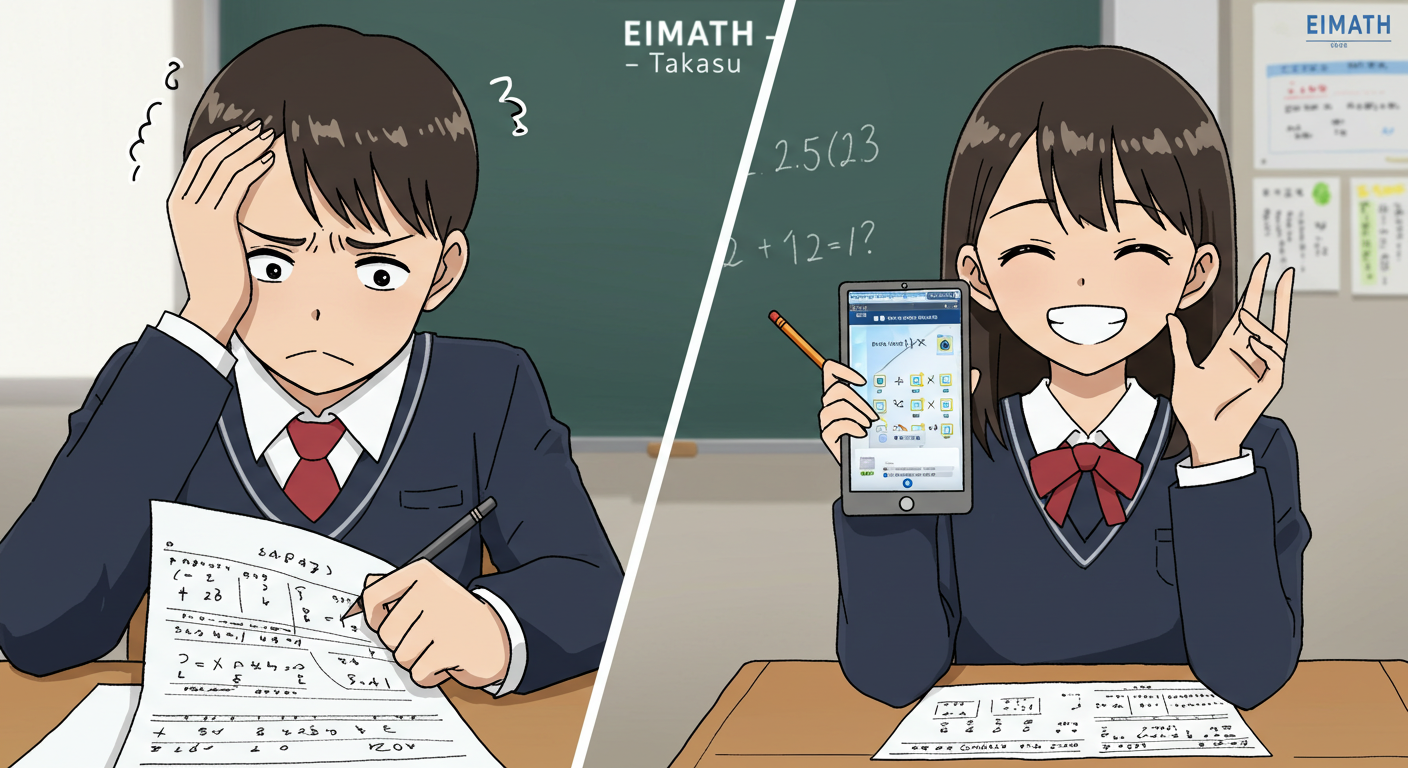
コメント